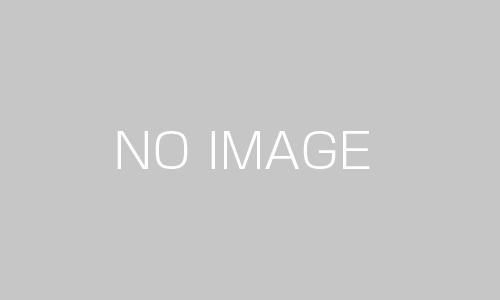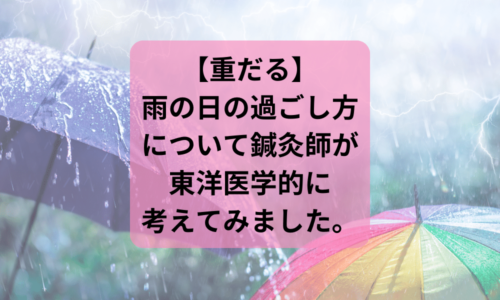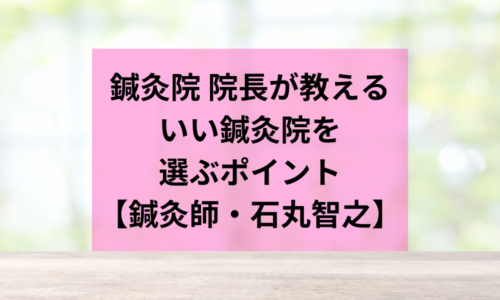- ホーム
- 副鼻腔炎
副鼻腔炎
-

【後鼻漏】実際に鍼灸師が施術で使用しているツボを紹介しちゃいます!!
みなさん、こんにちは。いつもブログをご覧くださり、ありがとうございます。武蔵小杉鍼灸接骨院の石丸です。本日は【完全版!後鼻漏のツボのまとめバー…
-
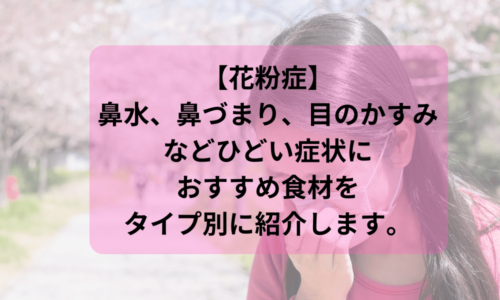
【花粉症】鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどひどい症状におすすめ食材をタイプ別に紹介します。
いつもブログを読んでくださって、ありがとうございます。今年も花粉シーズン真っ只中となりました。花粉症の方は、今年(2024年)は花粉がひどいと…
-
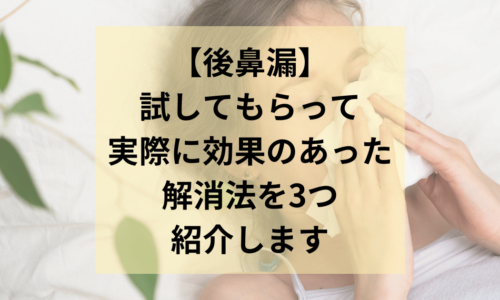
【後鼻漏】試してもらって実際に効果のあった解消法を3つ紹介します
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております、武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。いつもブログをご覧くださり、あ…
-

【免疫】感染症に強くなる!あの食材で免疫力をより高める効果的な方法
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております、武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。いつもブログをご覧くだ…
-
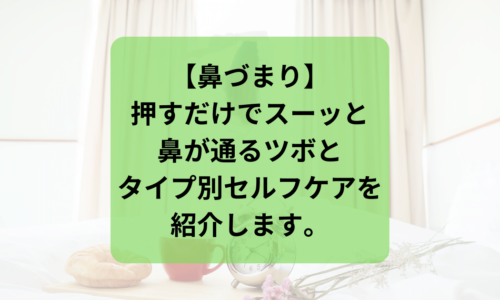
【鼻づまり】押すだけでスーッと鼻が通るツボとタイプ別セルフケアを紹介します。
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております、武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。本日もブログをご覧くださり、あ…
-

【後鼻漏】低気圧で悪化する鼻水をたった20秒で解消する方法を紹介します!
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております、武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。本日もブログをご覧くだ…
-

【慢性上咽頭炎】セルフケアで実際に効果のあった解消法3選をご紹介します!
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております、武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。本日もブログをご覧くだ…
-

【後鼻漏】急性?慢性?あなたのタイプに合った後鼻漏のツボを紹介します!!
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。本日もブログをご覧くださ…
-
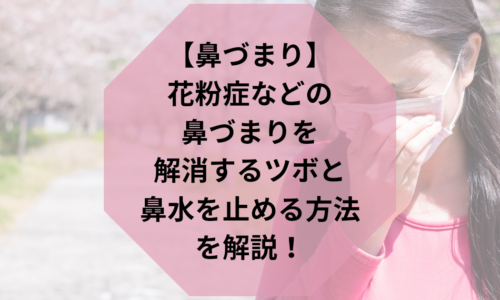
【鼻づまり】花粉症などの鼻づまりを解消するツボと鼻水を止める方法を解説!
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。本日もブログをご覧くださ…
-

【後鼻漏】鼻詰まりのツボ《上印堂》は、冷やすか?温めるか?についてお答えします!!
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。本日もブログをご覧くださ…