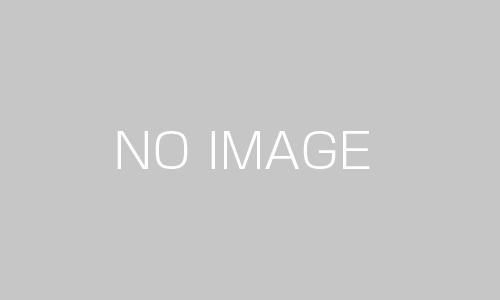- ホーム
- セルフケア
セルフケア
-
【二日酔い解消】効果的な食べ物とツボ押しで速攻回復!【鍼灸師が解説】
「二日酔いで辛い…」「早く楽になりたい…」そんなあなたへ。今回は、二日酔い解消に効果的な食べ物とツボをご紹介します。二日酔いの原因…
-

【頻尿】女性専用!困った頻尿の原因と自宅でできるセルフケアを紹介します
何だか最近トイレが近い外出先でいつもトイレを探しているトイレが心配で長距離の移動ができないトイレのせいで熟睡できない本日は、こんなお悩みの女性にお届け…
-

【頻尿】男性専用!!夜間・日中どっちも。頻尿の原因と対策を解説していきます!
こんにちは!神奈川県川崎市武蔵小杉駅から徒歩4分のところで鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院の石丸です。いつもブログをご覧くださり、ありがと…
-

【後鼻漏】実際に鍼灸師が施術で使用しているツボを紹介しちゃいます!!
みなさん、こんにちは。いつもブログをご覧くださり、ありがとうございます。武蔵小杉鍼灸接骨院の石丸です。本日は【完全版!後鼻漏のツボのまとめバー…
-
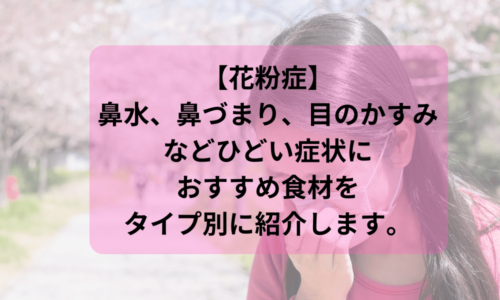
【花粉症】鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどひどい症状におすすめ食材をタイプ別に紹介します。
いつもブログを読んでくださって、ありがとうございます。今年も花粉シーズン真っ只中となりました。花粉症の方は、今年(2024年)は花粉がひどいと…
-

【視力】30秒つまむだけですっきり!よく見えるようになるツボをご紹介します。
最近、目がかすんで見えにくい。物が二重に見える。そんな症状でお困りの方は、今日紹介するツボを刺激してみてください。みなさん、こんにちは。武蔵小…
-

【めまい】メニエール病には足の裏!解消するツボを紹介します。
いつもブログをご覧くださり、ありがとうございます。本日は回転性のめまい、吐き気、耳鳴り、難聴などがあらわれる《メニエール病》を解消するツボの紹…
-
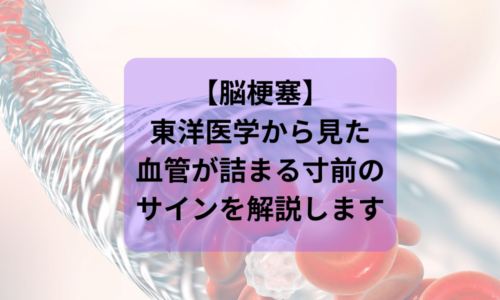
【脳梗塞】東洋医学から見た血管が詰まる寸前のサインを解説します
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。いつもブログをご覧くださ…
-

【腎臓】おすすめ!腎臓を元気にする食べ物を3つ紹介していきます。
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。いつもブログをご覧くださって、あ…
-
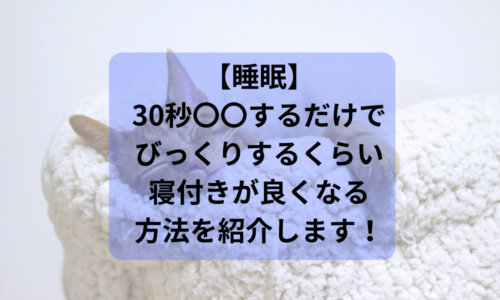
【睡眠】30秒〇〇するだけで、びっくりするくらい寝付きが良くなる方法を紹介します!
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。いつも動画をご視聴いただ…