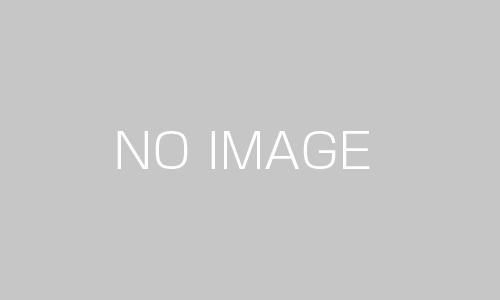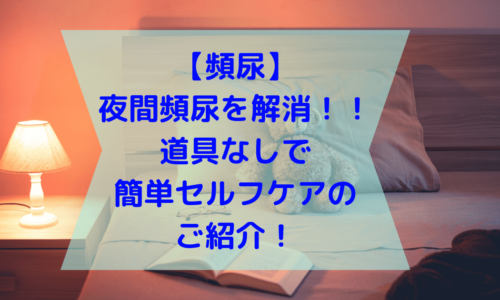- ホーム
- 経絡治療
経絡治療
-

【後鼻漏】実際に鍼灸師が施術で使用しているツボを紹介しちゃいます!!
みなさん、こんにちは。いつもブログをご覧くださり、ありがとうございます。武蔵小杉鍼灸接骨院の石丸です。本日は【完全版!後鼻漏のツボのまとめバー…
-

【視力】30秒つまむだけですっきり!よく見えるようになるツボをご紹介します。
最近、目がかすんで見えにくい。物が二重に見える。そんな症状でお困りの方は、今日紹介するツボを刺激してみてください。みなさん、こんにちは。武蔵小…
-
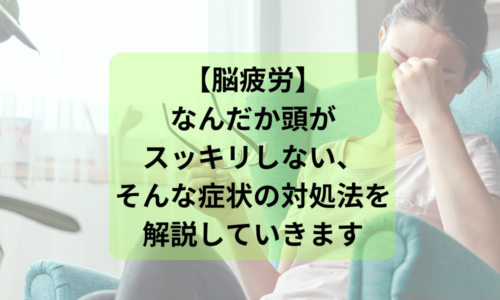
【脳疲労】なんだか頭がスッキリしない、そんな症状の対処法を解説していきます
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。いつもブログをご覧ぐださ…
-

【ツボ】合谷の正しい探し方。手順は3つ!実際にやりながら説明します!
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。いつも、ブログをご覧くださってあ…
-
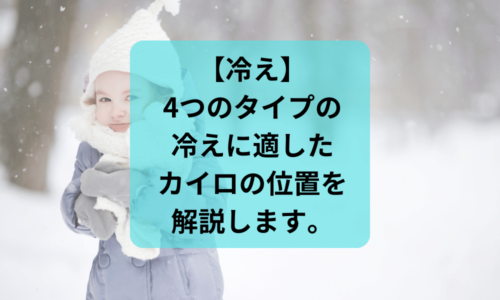
【冷え】4つのタイプの冷えに適したカイロの位置を解説します。
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。いつもブログをご覧くださ…
-

【逆子】有名なお灸と実際に鍼灸師が使っているコツを全て教えます!!
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。いつもブログをご覧くださ…
-
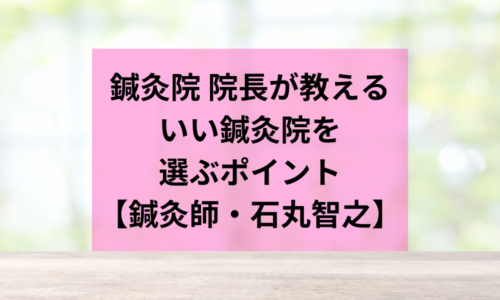
鍼灸院 院長が教えるいい鍼灸院を選ぶポイント【鍼灸師・石丸智之】
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。いつもブログをご覧くださって、あ…
-

【水分】自分に合った水分量を知る方法!本当に2ℓ必要なのか?!
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵杉で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。いつもブログをご覧くださって…
-
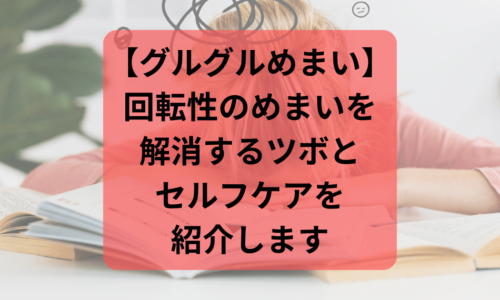
【グルグルめまい】回転性のめまいを解消するツボとセルフケアを紹介します
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております、武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。本日もブログをご覧くだ…
-
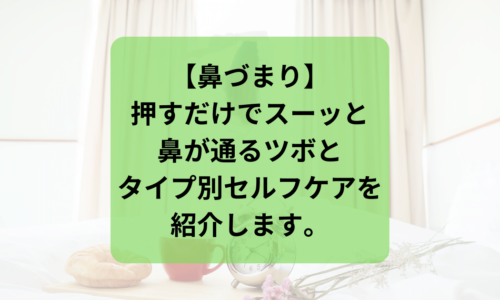
【鼻づまり】押すだけでスーッと鼻が通るツボとタイプ別セルフケアを紹介します。
みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております、武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。本日もブログをご覧くださり、あ…