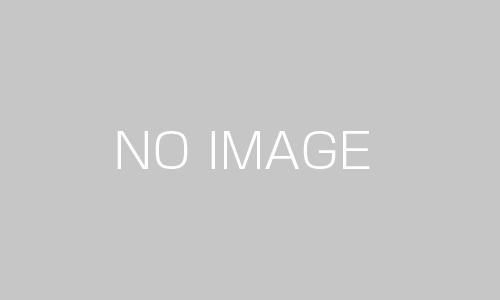- ホーム
- 未分類
未分類
-

むくみを自力で解消!鍼灸師が教える「あずき水」の作り方と特効ツボ
みなさん、こんにちは。 武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。 本日もブログをご覧くださりありがとうございます。本日は、むくみに効く食べ物「小豆(あずき…
-

鼻水が喉に流れる「後鼻漏」を自力で改善!鍼灸師が教える2つの特効ツボと意外なコツ
みなさん、こんにちは。 武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。 本日もブログをご覧くださりありがとうございます。「鼻水が喉の方に流れてきて、ずっと喉がイ…