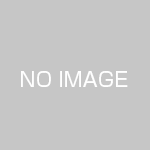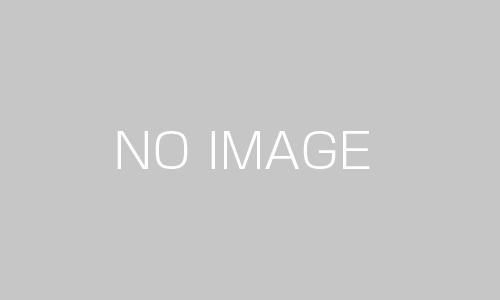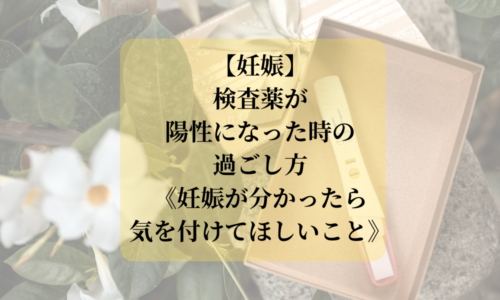みなさん、こんにちは。
神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。
本日もブログをご覧くださって、ありがとうございます。
鍼灸と検索すると腰痛で検索している方が多いようですね。
確かに「ギックリ腰で動けなかったけど鍼灸で1回で良くなったよ」とか「動けないくらいの腰痛だったけど鍼灸でスッキリ良くなった」など鍼灸師としては嬉しい話を耳にすることはあります。
しかし鍼灸師は十人十色。皆それぞれの理論をもって施術しています。上記の良くなった方々が違う理論の鍼灸院へ行っていたらどうだったのか鍼灸師としても気になる所です。
本日は武蔵小杉鍼灸接骨院の【腰痛の鍼】について書いていきます。
目次
腰痛になりやすい季節

風邪のように腰痛も起こりやすい季節があります。
まず1つ目は寒暖差が大きくなる時期です。10月にもなってくると朝晩の気温差が出てきます。実は寒暖差が大きい時期は腰痛も増えます。
次いで多いのが台風や梅雨など気圧が下がるときです。
ギックリ腰のような急性腰痛ではないですが、寒くなると腰痛が悪化する方もいらっしゃいます。
時期とは少し違うのですが、お仕事の長期休みに入ると毎回風邪をひいたりする方がいらっしゃいますが、腰痛や寝違えなどの症状が出る方もいらっしゃいますね。
腰痛のきっかけ

腰痛というと重い物を持った時に痛めるイメージを持っている方が多いと思います。しかし、腰痛でいらっしゃった方に「痛めたきっかけは何かありますか?」と聞くと「特に重いものを持ったわけではないんですけど…」「心当たりは無いんです」と直接原因が分からないことがほとんどです。
朝起きたら痛かった、車から降りる時に痛めた、歩いてたら痛くなった、ずっと座っていて立ち上がる時に痛めた・・・などそこまで腰の負荷が無い状態で痛める人が圧倒的に多いです。
腰の痛み方

腰痛にも様々な種類があります。①どんな動作で痛むのか ②いつが特に痛いのか ③どんな痛みなのか これらは、どれもバラつきが出てきます。
①どんな動作で痛むのか
靴下が履けない、前かがみができないなどの前屈で痛むタイプ。
うがいをすると痛い、反ると痛いなど後屈で痛むタイプ。
立ち上がるとき、歩き始めが痛く動いていると気にならないなどの動作開始時痛タイプ。
寝ると、横になると痛いタイプ。
②いつが特に痛いのか
朝が痛い、夕方になると痛い、夜中が痛い、疲れてくると痛いなど時間で痛むタイプ。
③どんな痛みなのか
ズキズキ痛む、刺すように痛む、重たく痛む、シクシク痛む、ピリピリ痛む、張ったように痛む、腫れたように痛むなど痛み方にも違いがあります。

ここからは当院の腰痛について解説していきます。
武蔵小杉鍼灸接骨院の腰痛の考え方

私たちは体中にあるツボを使って施術します。腰が痛いので痛いところに鍼をするとお考えの方もいらっしゃいますが、ツボを使う場合は患部に触れなくても痛みが治まることも珍しくありません。
ツボの中でも腰と関係が深いのは《腎》のツボのグループです。これを施術の時にお伝えすると「腎臓と腰がなんの関係があるの?健康診断では腎臓の数値なんて1回も注意されたことないんだけど」と思う方も多いです。西洋医学と東洋医学の理論はちょっと(結構ですかね…)違うので「東洋医学ではこう考えているよ~」くらいに思っていただければと思います。
《腎》のツボが元気だと普段から腰も元気だけど何らかの理由で《腎》ツボの元気がなくなると腰も痛くなるので、《腎》のツボの元気が戻るように施術します。《腎》は冬や寒さに弱いため、元々寒がりな方が多く冬に腰痛だけではなく他の体調に関しても悪い方が多い印象です。
この《腎》のタイプの腰痛であれば↓↓のツボが有効なこともあります。
https://www.instagram.com/p/CURr0Q0rjSk/?utm_source=ig_web_copy_link
腎の腰痛《腎のケア》
腎のタイプの腰痛の方には、腰痛以外にも頻尿や耳鳴り、腰痛ともちょっと違う腰に力が入らないような症状や、唾液が少なく口が乾く感じが感じられたり、不安感などメンタルの調子が悪くなるなどの症状がみられることもあります。
関連動画⇒【重要】腎臓が弱ってるサインと対処法やツボを紹介します
関連記事⇒【腎臓の弱り】東洋医学から見た腎臓が弱ってるサインとおススメの食べ物やツボを紹介します
今日は腎のケアとして、腎の機能を高めてくれる食べ物をご紹介していきます。
腎は黒い食べ物がいいとされています。なぜ、黒い食べ物がいいのかといいますと、腎のツボのグループという考え方は腎以外にも4つの臓器のグループが存在します。次の項目でも出てくるのですが《肝》《心》《脾》《肺》《腎》と全部で5つのグループに分かれるんですね。
東洋医学には五行といって、物事を5つに分ける考え方があります。季節、感覚器、感情などさまざまなものを5つに分類するのですが、色を5つに分類したときに腎と同じグループに入るのが《黒》なんですね。
ですので、黒い食べ物と腎は昔から相性がいいとされてきました。
黒い食べ物の具体例としましては
- 黒豆
- 黒ゴマ
- 黒キクラゲ
- ひじき
- 昆布
などになります。このような食品を、定期的に食べていただけると腎の機能が元気になっていきます。
また、身体に関する液体(涙や汗、唾液など)を5つに分類したときに腎と同じグループになるのは《唾液》です。唾液はよく噛んで食べるとたくさん出てきますので、食事はゆっくりよく噛んでいただくことも腎にとってはプラスに働きます。
食べ物以外のケアの方法として、ツボを刺激する方法があります。
分かりやすいツボとしましては足にある【太渓】(たいけい)がおすすめです。
太渓は腎のツボのグループの中の1つになります。ツボの効能はは益腎(えきじん)といって腎の機能を高めてくれるツボとされています。
場所は足にあるので一人でも簡単に刺激がしやすいと考えて、このツボを選びました。太渓のツボの探し方は、過去に動画とブログで解説していますので、詳しく知りたい方はこちら⇒動画【太渓】ツボの正しい探し方。手順は3つ!実際にやりながら説明します! ブログ【ツボ】腎のツボ《太渓》正しいツボの探し方を3ステップで解説します。をご覧ください。
ツボ押しもいいのですが、温めてあげる方がより一層効果的だと思います。自宅で気軽にできるお灸もいいですし、火を使うお灸が心配な方はペットボトル温灸やカイロ、電子レンジでチンして使う小豆の温灸で温める方法もありますので、やりやすい方法で温めてみてください。
自宅でお灸の動画⇒【お灸のやり方】自宅でのお灸のやり方を紹介します。
その他のツボを温める方法の動画⇒【煙も匂いも出ない】火を使わないお灸を紹介します
ブログ⇒【ペットボトル温灸】火を使わない、煙も出ない、お手軽簡単なお灸を紹介します。
他のタイプの腰痛
もちろん全ての方の腰痛がこの《腎》に当てはまるわけではありません。例えば上で書いたように寒暖差が激しくなると出る腰痛は《肺》のツボの弱りと考えることが多いです。寒暖差が大きいと《肺》のツボは調子を崩します。腰痛だけではなく《肺》の調子なので喘息が出やすくなったり風邪をひきやすくなったりと呼吸器の症状も出やすい季節となります。他にも睡眠が浅くなったり、皮膚症状が出やすくなることもあります。
前屈で痛むのは《肝》のツボの腰痛と考えていて、《肝》は筋肉の血流とつながりが深いため《肝》の調子が悪くなると筋を痛めやすくなります。他にも《肝》の調子が悪いと頭痛が起きやすい、目が疲れやすい、イライラするなどの不調も起こりやすいです。
肝についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください↓↓
ブログ⇒【梅核気】喉のつまり・咽喉頭異常感症・ヒステリー球を解消する飲み物、食べ物、生活習慣の紹介!!
動画⇒【喉のつまり】ヒステリー球(梅核気)を解消する食べ物3選
施術をするときに考えてること
これまで《腎》とか《肺》とか《肝》とかツボのグループの話をしてきましたが、体中に361このツボがありまして、これは5つのグループに分かれてます。その5つのグループというのが《肝》《心》《脾》《肺》《腎》の5つです。

上記の図のように、5つのグループはバランスをとっていますが、これが崩れると調子が悪くなります。私たちは崩れたバランスを戻すためにツボの計算をします。
この、5つのグループを【五臓】(ごぞう)と呼びますが、東洋医学ではこの五臓を使って施術していきます。上記の図では円を描く矢印と、輪の中にある星を描く矢印がありますね。円を描く矢印は、矢印の向きに【気】が循環していると考えます。この気がどこかで、流れが悪くなったり詰まってしまうと、それは身体に症状として出ます。
先にも述べましたが、腰痛の原因に天候の変化や季節の変化が関係してきますが、寒暖差は肺のツボにダメージが大きかったり、寒さは腎のツボに影響が大きいことでバランスを崩し腰痛になると考えています。
他にも、イライラや不安などの感情も、この五臓には影響します。イライラなどの怒りは肝のツボの消耗につながり、不安などは腎、悲しみは肺のダメージになるため、精神的なものが腰痛の原因になることも十分に考えられます。
まとまった休みに入ると体調を崩す方などは、上記の図のバランスが一気に崩れてしまうためにおきるとみています。
ツボのバランスが整えば症状は治まるので、患部に直接鍼をしなくても症状が緩解すると考えています。
まとめ
まとめますと、腰痛にもなりやすい季節があり、それは寒暖差が大きくなる季節と台風などの低気圧になることが増える時期。また、寒さでも悪化する。
実は、これといったきっかけが無い方が多い。
痛み方も様々で、痛む姿勢、痛むとき、どんな痛みなのかを知る。
武蔵小杉鍼灸接骨院では、腎のツボを使うことが多い。腎以外でも、肝のツボのタイプ、肺のツボのタイプなど、腰痛は東洋医学的に見ても様々な原因がある。
本日は、武蔵小杉鍼灸接骨院が考える腰痛について解説していきました。