冬になると、なんだか起きられない。
寒くて布団から出られない。
日々さまざまな患者さんと接する中で、この時期になると増える相談が『起きられない』なんですね。
病院に行くほどではないけれど、毎朝しんどいのも大変です。そんな方に少しでも役立てていただけたら幸いです。

みなさん、こんにちは。
神奈川県川崎市武蔵小杉駅で鍼灸接骨院をやっております武蔵小杉鍼灸接骨院 院長の石丸です。
本日もブログをご覧くださって、ありがとうございます。
今回はですね、私がおすすめする【冬の睡眠方法】について説明していきますね。
目次
この順番で紹介していこうと思います。お忙しい方はまとめだけ読んでいただければ分かるようにしてありますので、必要なところだけでも読んでいってください。
それでは、よろしくお願いします。
冬の睡眠時間
まずは簡単に、東洋医学の中の睡眠の考え方について解説していきます。東洋医学では物事を【陰陽】(いんよう)に分けて考えます。

陰陽の例え
- 植物と動物
陰⇒植物(動物と比べて動かない)
陽⇒動物(植物と比べたら動く)
- 水と火(これは、分かりやすいですね)
陰⇒水(火と比べたら冷たい)
陽⇒火(水(お湯だとしても)と比べたら熱い)
- 男性と女性(男女の陰陽は身体的な特徴から分けられています)
陰⇒女性
陽⇒男性
- 葉物の野菜と根菜
陰⇒葉物の野菜
陽⇒根菜(葉物と比較して、地球の中心に向かって育つことや中身が詰まっていて硬いから陽になる)
このように、静かなもの、冷たいものなどは陰に分類され、動くもの、温かいものなどは陽に分類されます。(説明が浅いのですが、本来はもっと細かな分類があります)
このように、東洋医学にはさまざまなものを陰陽に分けて考えます。これは物質がある『物』だけではなく、時間や天気、季節などすべての物事を陰陽に分類します。
1日の活動も陰と陽に分けることができ、睡眠というのは電源がOFFになる感じで動かなくなることなので陰になりますね。睡眠が陰なので、起きて活動することは陽となります。
これを踏まえて、冬の睡眠時間をどうすればいいのかと考えますと、冬というのは陰が強くなる時期と考えますので、結論《睡眠時間を長くとってもいい時期》と考えます。
冬というのは、暗くなるのが早くて明るくなるのが遅いですね。これってつまり、日の出が遅くて日の入りが早いってことになります。
冬は1年の中でも陽の時間が短くて、陰の時間が長い季節と考えますので、冬の睡眠のとり方としては【早く寝て遅く起きる】というのがいいとされています。
太陽と同じようなリズムで生活するのがいいってことですね。
冬の睡眠はいつもより早く寝て、少しだけゆっくり起きるっていうのが私のおすすめする睡眠のとり方になりますね。
少しだけゆっくり起きるのは、具体的に何分くらい?と思う方もいらっしゃると思いますが、いつも起きる時間より長くても大体30分くらいで調整してねっていわれてます。例えば、いつもAM7:00に起きる方なら7:30までに起きてねってことで、あまり長く寝すぎてもそれはそれで生活のリズムが崩れちゃいますので、長くても30分ですね。
冬の睡眠方法

続きまして、私がおすすめする冬の睡眠方法ですね。
これは【北枕】がおすすめです。
みなさんから、睡眠の相談を受けるなかで1番多いのは『枕が合ってないんですかね~?』『どんな枕を使えばいいですか?』など【枕】の相談は本当に多いです。しかし、向きを気にされる方は全くいらっしゃいません。
私は枕に関しましては、何を使ってもいいと思っています。枕無しでもいいくらいです。理由としましては、子どもって枕の有り無し関係なくしっかり眠れている子が多いんですよ。それって、枕の問題ではなくて身体の方の問題なんですね。もちろん、物理的な枕や寝具が睡眠にいい影響、悪い影響を与えていることもあると思います。しかし、みなさんから受ける相談って枕やマットレスを何に変えても問題が解決しないんです……というものが多いです。なので、枕は何でもよくて、その使い方に着目したってことなんですね。
北枕は縁起が悪いとも言われますので、そういったことに抵抗のある方は無理にはおすすめしないんですけど、私は冬の睡眠には北枕をおすすめしますね。
なぜかといいますと『頭寒足熱』(ずかんそくねつ)という言葉があるんですけど、頭が冷えてて足が温かい状態ですね。頭が冷えていると、睡眠ホルモンとも呼ばれていますメラトニンが、よく出るようになりますね。メラトニンによって熟睡しやすくなったり、睡眠の質を上げることができるんです。
頭寒足熱は東洋医学的にも、とても健康な状態と考えますね。
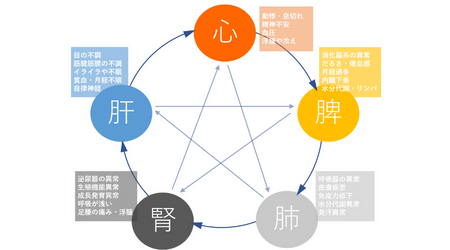
東洋医学でよく使われる木、火、土、金、水に方角を当てはめると北は水にあたります。反対の南は火になりますので、北枕にすることで頭を水の方、冷やす方に向けることができ、足は南になるので温める方へ向けることができます。
縁起とか気にされないのであれば、北枕をおすすめしますね。(受験生にも北枕はいいといわれていますね。勉強でフル回転した脳をクールダウンさせるという意味だと思います。)
冬の朝の起き方
次にですね、冬の朝の起き方ですね。
冬の朝はとても寒いですので、いきなり温かい布団から寒いところにバッと出ますと寒暖差で身体が疲れたりしますので、まずは布団の中で軽く動いて身体を温めてから、少しずつ布団からでるのがいいとされています。
私がよくおすすめしているのは、朝起きたら布団の中で手足をグーパー動かすのを20回やってくださいとお伝えしています。
布団の中でですね手も足もグーパーグーパーと動かすことで、末端にまで血を送ってるんですね。末端に血を送ることで、身体を温めて起こします。
※夜間の睡眠時間(動かない静かな時間)は、その方が元々持っている気血を流す力によって目覚めの良し悪しは変わってきます。寒くなければ、サッと起きられる方は就寝中の気血の流れがよく、起きる時間が近づいてくると気血の流れを増やしていきスッキリ目覚められます。
就寝中の気血の流れが悪い方は、起きる時間になっても気血が増えないため、起きるときに頭や身体を起こすのに使う筋肉への循環が悪くスッキリと起きられないと考えられていますので、元々寝起きが悪い方は冬に限らずグーパーしてから起きる癖をつけると、少し起きやすくなるかもしれません。
おススメの記事⇒【自律神経失調症】絶対にやって欲しい朝の習慣2つと効果的なツボをご紹介します!!
オススメのYouTube⇒【自律神経失調症】絶対にやって欲しい朝の習慣!不眠などにも効果的
まとめ
まとめますと、冬の睡眠時間は早めに寝て少しゆっくりめに起きることですね。時間は30分以内で調整すること。
冬の睡眠方法は北枕がおすすめ。北は頭を冷やしスッキリさせ、睡眠に必要なホルモン《メラトニン》が
冬の朝の起き方は、まず布団の中で手足をグーパーさせて末端に気血を届かせて、ゆっくり身体を目覚めさせてから起きる。これが、おすすめです。
本日はですね、冬の睡眠方法について説明していきました。
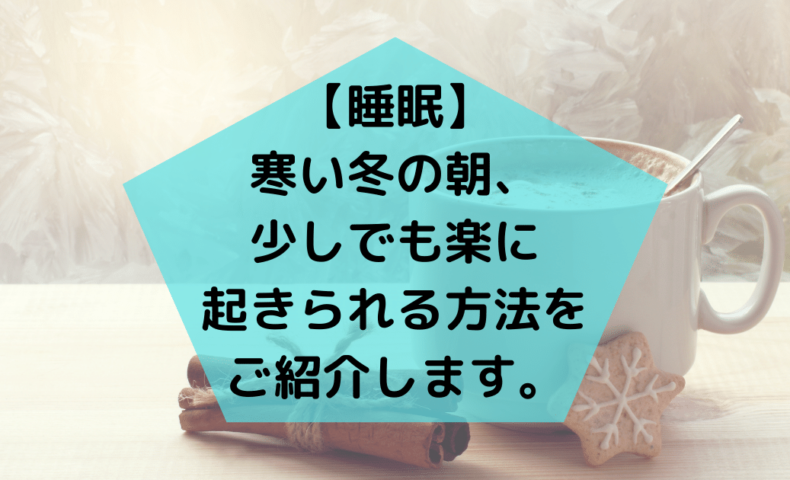

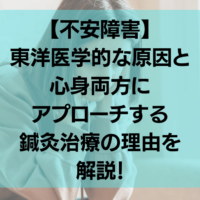
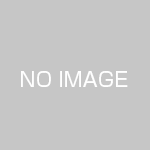


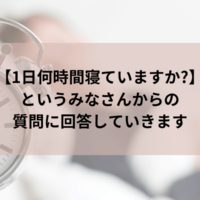


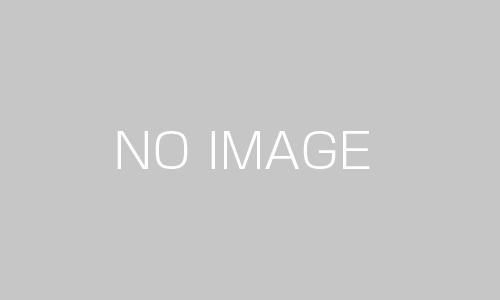

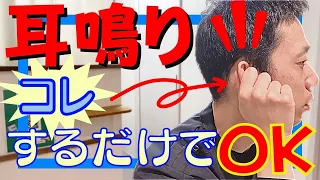
この記事へのコメントはありません。